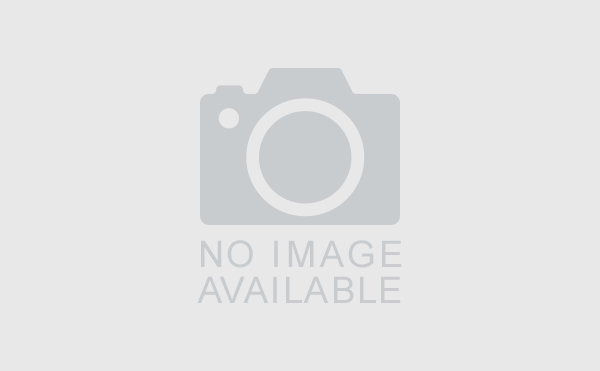■モチベーションは誰の手に?
社員の不満、離職問題....。事前の兆候把握が極めて困難な環境においては、従業員の満足度調査も一つの手段として有効視される。この内部環境課題への取組みもまた、活性化への道筋である。ただし、この取組みは社内外に評価を得る一方で、一歩間違えば経営全般、なかんずく人材育成への課題を改めて生じさせる。そもそも、雇用関係成立とは、双方が対等な関係性をもってして、社会活動の主体を実現させるものである。では、労働者個々のモチベーションは誰がどのようにコントロールすべきか?対価を払う側が期待すること、それは価値提供側が業務遂行するにあたって仕事への熱量を最高点に到達させていることがスタートラインである。そのモチベーションは誰かに用意されるものではない。仕事を請け負う者が自らコントロールした上で臨むものであり、俗にプロと言われている。労働者は対価が保証されているということ、その責務を果たすことを忘れてはならない。雇用側に求めらるものは、労働者の低下したモチベーションのフォローでだけではなく、仕事以外の様々な家庭問題も含めてモチベーションが変化する労働者に対して、業務中はスイッチを切り替えることを可能とするプロ意識の醸成が先決かもしれない。
さて、経営層、雇用側のモチベーションはどうだろうか?モチベーション低下の社員の存在を受けてモチベーションを低下させていないだろうか?踊らされてはならない。そこに時間を取られてはならない。